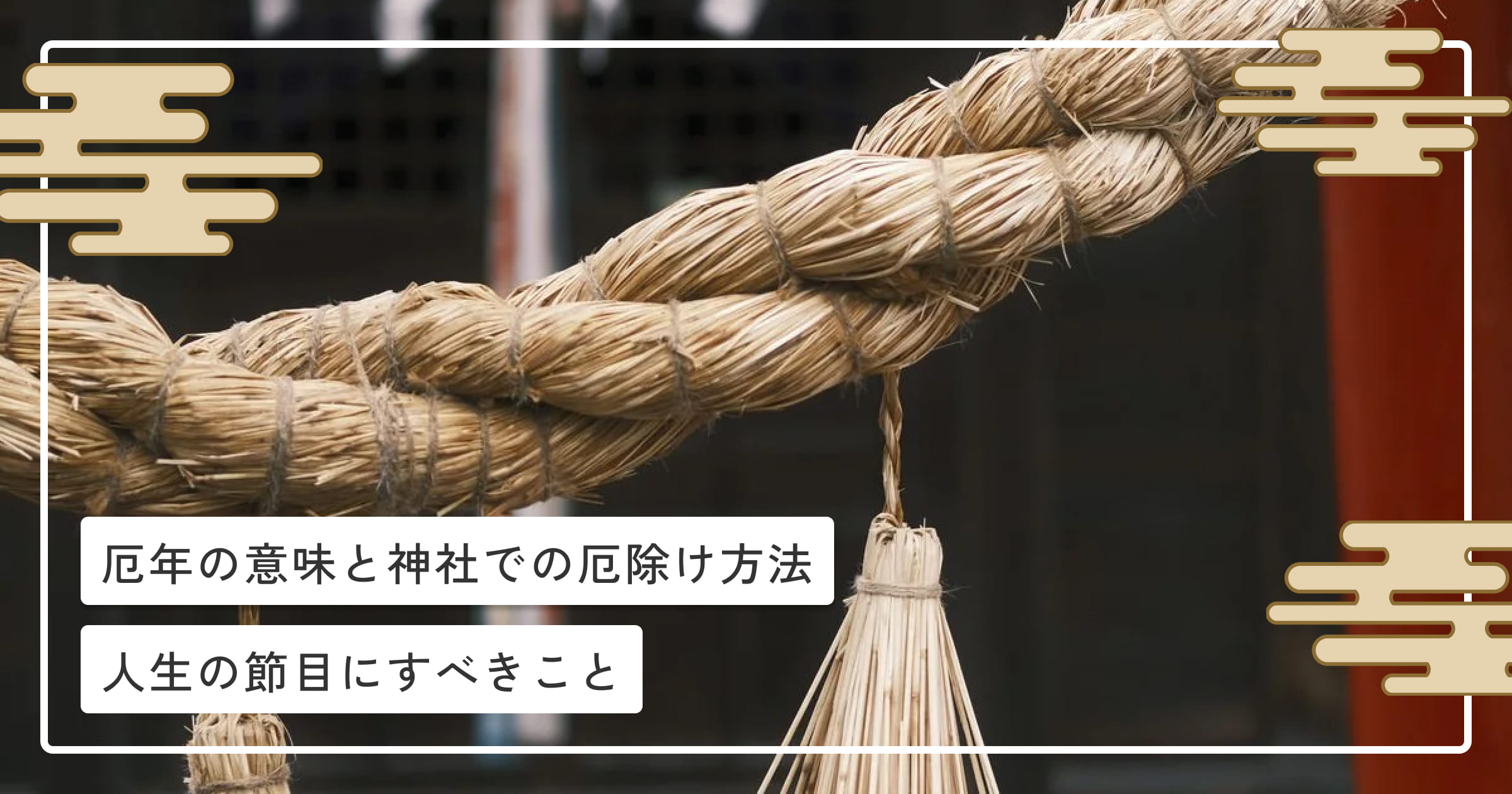
厄年の意味と神社での厄除け方法|人生の節目にすべきこと
「厄年(やくどし)」という言葉は耳にしても、具体的な意味を知らない人も多いでしょう。
厄年は「災難が起こりやすい年齢」とされ、古くから神社で厄払いの祈祷を受ける文化があります。
この記事では、厄年の意味・年齢・由来・過ごし方をわかりやすく解説します。
厄年とは?
厄年とは、人生の節目で災厄が訪れやすいとされる年齢のこと。体の変化や社会的責任が増える不安定な時期とも重なります。
厄年の由来
概念は平安時代にさかのぼり、陰陽道や仏教思想が基になったとされます。転機の年齢=厄災が重なるという捉え方です。
厄年の年齢
厄年は数え年で計算します。代表的な年齢は以下のとおりです(神社により差異あり)。
- 男性:25歳・42歳(大厄)・61歳
- 女性:19歳・33歳(大厄)・37歳
厄年に起こりやすいこと
災難=病気や事故だけではありません。以下のような変化も「厄」に含まれます。
- 体調を崩しやすい
- 家族や仕事でのトラブル
- 転職・転居など環境の大きな変化
- 精神的な不安や焦り
必ず起こるわけではありませんが、「注意すべき年」と意識することが重要です。
厄年の過ごし方と対処法
-
神社で厄除け・厄払いを受ける
正月〜節分に祈祷を受ける人が多く、神様のご加護を願うとともに不安を和らげます。
-
心身のケアを最優先
睡眠・食事・ストレス管理を徹底し、無理をしない生活を心がけましょう。
-
環境や人間関係の見直し
信頼できる人との関係を深め、自分の行動を振り返る好機と捉えましょう。
厄年は「悪い年」ではない
厄年は転機や節目ともいえます。自分を見直し、新しいスタートを切るチャンスです。
まとめ
厄年は、人生の節目を意識し心と体を整えるための日本独自の知恵です。不安を感じても「注意して過ごす」だけで多くの災いは防げます。神社で厄払いを受け、穏やかに一年を過ごしましょう。